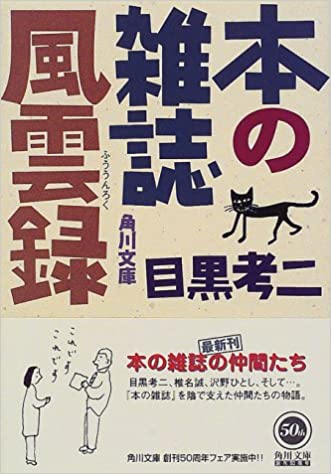
昨日、明治記念館であった「目黒考二さん、北上次郎さん、藤代三郎さんの思い出を語り合う会」に行って、お土産に渡された紙袋の中に入っていた本。もちろん、出た時に読んでいる。自分の読書記録をチェックすると1985年6月7日に読んでいた。それから40年近くたってしまった。本書を読んだ時点では、自分は「本の雑誌」のいち読者に過ぎず、その後、目黒考二さんと面識を得て、「本の雑誌」に原稿を書かせてもらうことになろうとは思ってもいなかった。
本書は「本の雑誌」の創刊にいたる経緯と、その後の「配本部隊」の10年間の物語である。「配本部隊」とはなにか? 取り次ぎを通していなかった本の雑誌社の本を、直接書店に届ける助っ人学生たちのことである。バイト代も出ないのに、本の雑誌社に集まっては仕事を手伝う様々な学生たちのことを、著者は愛情をこめて本書で紹介していく。こういう若者たちに支えられて、「本の雑誌」という奇妙な雑誌は育ってきたのだ。
今回読み直してみて、すっかり忘れていたことがあった。107ページに登場してくる高橋秀博というのは、「幻影城」ファンクラブとして発足した「怪の会」の設立者の高橋秀博のことだろう。もちろん、初めて読んだ時にも気が付いていたはずだが、そのことをきれいさっぱり忘れていた。
数多くの学生が登場してくるが、なんといってもいちばんインパクトがあるのが吉田伸子さんだ。助っ人学生なのに、キャラが立ちすぎ。
いろいろ懐かしい思いにかられて再読して、最後の一文で泣かされてしまう。
「この雑誌がたとえ廃刊になり、彼らがここで過ごした日々を忘れても、ぼくが覚えている限り「本の雑誌」はぼくの中にあり続けるだろうと考えていた。ぼくにとって「本の雑誌」とは、彼らだったのである。」
「あとがき」の最後のフレーズにも泣かされてしまう。
「ありがとう。君たちのことは忘れない。」
吉田伸子さんの「解説」の最後のフレーズにも泣かされてしまう。
「目黒さん、また飲もうね。」
「ぼくが覚えている限り」と言いながら、もう目黒さんはいらっしゃらない。「また飲もうね」と思っても、もう一緒に飲むことはできない。でも、目黒さんと一緒の時間を過ごした助っ人学生たちがいる限り、目黒さんは彼らの中に生き続けるのだろう。